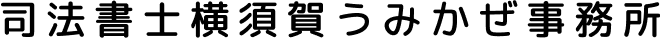遺留分侵害請求の期限~時効を止める方法とは~
相続の際に、誰がどの程度財産を相続するのかを気にする方は多いのではないでしょうか。
場合によっては、遺留分を侵害している相続に立ち会ってしまうこともあります。
遺留分を侵害されている際にとるべき行動については、期限が定められています。
今回は、遺留分侵害額請求の期限と時効を止める方法について 解説します。
■遺留分侵害額請求の期限
遺留分とは、民法により保障された法定相続人が最低限相続できる財産の割合をさします。
法定相続人は、この遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求を起こすことで遺留分に相当する金額を請求できます。
しかし、遺留分侵害額請求はいつでも行使できるというわけではありません。
この遺留分侵害額請求を行使できるのは、
・相続開始および遺留分侵害を知った時から1年
または
・相続の開始から10年
が経過するまでです。
前者については、単に相続が発生していることだけを知っているだけではなく、その相続において自身の遺留分を侵害されていることまで も知っている必要があります。
なお、遺言が無効であると考えられる場合においても、原則的に時効は進行するため、のちに述べる時効を止める方法をとることをおす すめします。
後者については、除斥期間相続の開始と遺留分侵害のどちらも知らなくても、時効は進行します。
■時効を止める方法
1.配達証明付内容証明郵便
時効を止めるためには、遺留分を侵害している相手方に「遺留分侵害額請求を起こす」という意思表示を行わなくてはなりません。
具体的には 下記の事項を記して配達証明付内容証明郵便を送ります。
・請求する本人と相手方の氏名
・請求の対象となる遺贈や遺言などの特定
・遺留分侵害額 に相当する分の金銭の支払を請求すること
・請求日時
後から、請求があったかどうかで争った際に、請求したことを証明するために口頭などではなく、配 達証明付内容証明郵便で送る必要があります。
2.遺留分侵害額請求を起こした後にするべきこと
遺留分侵害額請求を起こした後にもやるべきことはあります。
遺留分侵害額請求により金銭支払請求権という新たな別の権利が発生します。
そして、この金銭支払請求権にも5年という時効があります。
したがって、この金銭支払請求権も時効が切れる前に行使しなくては、たとえ遺留分侵害額請求を起こしたとしても、遺留分に相当する金銭の支払請求ができなくなってしまいます。
金銭支払請求権の時効を止めるためには、遺留分侵害額請求権に基づく金銭支払を求める裁判を起こすか、相手方に金銭を支払うことを承認させる必要があります。
なお、後者の場合は、時効の更新が起こり、時効がゼロから再びスタートします。そのため、相手方が承認してから再び5年が経過すると時効を迎えてしまうとなってしまうので注意しましょう。
■まとめ
今回は、遺留分侵害額請求の期限と時効を止める方法について解説しました。
遺留分侵害額請求は、場合によっ ては時効が1年と比較的短い期間といえます。
また、遺留分侵害額請求を起こした後も、必要な手順がある上、法律上の知識や経験が必要とされる場面も出てきます。
司法書士横須賀うみかぜ事務所は、神奈川県横須賀市を中心に、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町にて、みなさまからのご相談を承っております。
遺留分侵害額請求をお考えの際は、当事務所までご相談ください。豊富な経験と知識を武器に、みなさまの相続手続きを全力でサポートさせ ていただきます。
KNOWLEDGE基礎知識
-

遺言書
■遺言書とは遺言書とは、自身の死後、財産をどのように相続させるかを決定する意思表[...]
-

成年後見制度とは
成年後見制度は認知症や精神障害によって意思能力が低下してしまい、十分な判断能力が[...]
-

【司法書士が解説】借...
借地権を相続した場合、貸主に対して許可をもらったり、土地を返還したりする必要はあ[...]
-

【司法書士が解説】孫...
相続人となるはずの人がすでに亡くなっていたり、法律上の理由で相続できない場合に、[...]
-

相続登記を司法書士に...
不動産の所有者が亡くなった場合に名義変更をする必要があり、このことを相続登記とい[...]
-

家族信託で失敗しない...
■家族信託とは家族信託とは、簡潔にまとめると本人が自分で財産を管理できなくなった[...]
KEYWORDよく検索されるキーワード
PROFILE代表資格者
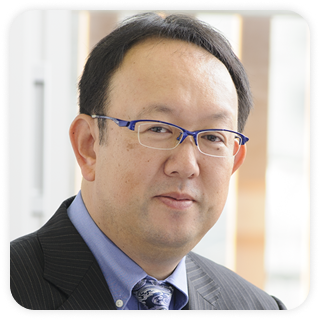
長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |