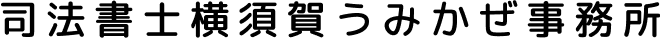遺留分
遺留分とは
遺留分とは、法律の定めによって相続人が相続できる最低限の割合のことです。遺言書を作成すれば、法定相続人やそれ以外の者に遺言者の全財産を遺贈することもできますが、それでは残された法定相続人が、本来受けられた相続分が相続されないという不測の事態になりかねません。そのような事態を避けるた めの制度が遺留分制度です。
遺留分侵害請求権
そこで、遺留分を取り返すためには、自己の遺留分の範囲までの財産の返還を請求する必要がありま す。それが遺留分侵害請求権です(民法1042条)。
改正前民法で「遺留分減殺請求権」と称されていたものが、2019年7月1日に施行された改正民法(相続法)では、「遺 留分侵害請求権」と称するようになりました。
遺留分侵害請求権の割合
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です(民法1042条1項)。つまり、被相続人(死亡した人)の配偶者、子、直系尊属(両親や祖父母など)には遺留分が認められています。
遺留分の具体的な割合は、法定相続人の親族 関係上の地位によって異なります。
・総体的遺留分
被相続人が残した相続財産の遺留分全体のことを総体的遺留分と呼びます。
直系尊属のみが相 続人である場合 相続財産の3分の1(民法1042条1項1号)
それ以外の法定相続人(配偶者のみ、配偶者と子ども、子どものみなど)の場合 相続財産の2分の1(民法1042条1項2号)
・個別的遺留分
実際に個人が得られる遺留分は、総体的遺留分とそれを受け取る遺留分権利者の地位によって割合は変化します。これを個別的遺留分と呼びます。
個別的遺留分は、総体的相続分と法定相続分(民法900条各号)を掛け合わせた割合が個別的遺留分となります。
具体例:相続人が配偶者と子ども
相続人はどちらも直系尊属でないので、総体的遺留分は2分の1(民法1042条1項2号)
両者の法定相続分は各2分の1(民法900条1号)
配偶者の 個別的遺留分は2分の1×2分の1=4分の1
子どもの個別的遺留分は2分の1×2分の1=4分の1の割合になります。
遺留分侵害請求の方法
・内容 証明郵便
遺留分侵害請求は、遺留分の侵害を知った時から1年以内に行う必要があります(民法1048条)。期限内に請求したことが示せるよう、最初に内容証明郵便によって相手方に通知書を送付します。
・話し合い
通知書が届いたら、遺留分の具体的な返還方法について相手方と話し合いを行います。被相続人から金銭の 贈与があった場合には、相当額の支払いによって返還を行うことができます。ただし、不動産の贈与では相当分の返還が難しくなります。不動産を共有状態にすることで返還 を行うこともできますが、一般的には金銭賠償を行います。これは、請求者と被請求者の間で対立が生じていることが多く、共有は双方にとって不都合になるからです。
・遺留分侵害額の請求調停
話し合いによっても解決が図れなかった場合には、家庭裁判所において遺留分侵害額の請求調停を行います。ここでは調停委員が間に入って話し合いを行うため、双方が顔を合わせることなく調停を進めることができます。
・遺留分侵害額請求訴訟
調停による解決できなかった場合、地方 裁判所で訴訟を行います。ただし、遺留分の価格が140万円以下の場合には、簡易裁判所で行うことになります。
ここでは、自身に遺留分侵害請求権があることを証拠によって示すことが必要になります。
司法書士 横須賀うみかぜ事務所では、横浜市(磯子区・金沢区・港南区・栄区)/逗子市/三浦市/横須賀市/葉山町/鎌倉市)の皆様を中心に、東京都の皆様から、債務整理、相続(遺言)、家族信託、法人(設立、法人登記)についてのご相談を承っております。
遺留分問題についてお悩みの際はお気 軽に司法書士 横須賀うみかぜ事務所までご相談ください。
KNOWLEDGE基礎知識
-

遺言書の代わりとして...
家族信託の仕組みを用いて遺言と同じような効力を発生させることもできます。これは、[...]
-

遺産分割
民法には、法定相続人が定められています。法定相続人とは、実際に遺産を相続するか、[...]
-

家族信託手続きの流れ
家族信託の手続きを行う際に気を付けなくてはならないのは、まず、誰を受託者にするか[...]
-

所有者が認知症になっ...
普段我々は何気なくものを売り買いしていますが、それも売買行為という立派な法律行為[...]
-

不動産に纏わる法律 ...
人が自分だけで独占的にものを占有できる権利を物権といいます。そしてその物権の中で[...]
-

横須賀市の相続が得意...
■相続に必要な対策とは相続に際しては、遺産分配のトラブルが生じやすいものです。ま[...]
KEYWORDよく検索されるキーワード
PROFILE代表資格者
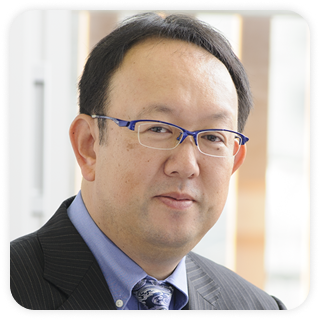
長坂 利広(ながさか としひろ)/ 司法書士
- 神奈川県司法書士会横須賀支部
横須賀の皆さまに寄り添うために
平成17年の開業以来、横須賀の皆さまに寄り添い、暮らしを支える法務サービスを提供してまいりました。
相続や登記は、人生の節目に関わる大切な手続きです。
だからこそ、専門家として「わかりやすさ」と「安心」を第一に心がけています。
どんな小さなご不安でも、どうぞお気軽にご相談ください。
地域に根ざした司法書士として、これからも皆さまのお力になれるよう努めてまいります。
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 司法書士横須賀うみかぜ事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒238-0003 神奈川県横須賀市稲岡町82番地 神奈川歯科大学内資料館1階 |
| 連絡先 | TEL:046-824-8366 / FAX:046-824-8367 |
| 受付時間 | 平日 9:30 ~ 17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 代表者 | 長坂 利広(ながさか としひろ) |